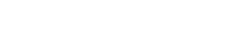Treatment
正しく噛むことが大切な理由

「噛む」という動作は、食事や会話、さらには呼吸など、私たちの生理機能や運動機能に密接に関わっています。
食事の際にしっかりと噛むことで、食べ物を噛み砕き、飲み込みやすい形にするだけでなく、体内での消化や栄養吸収を助ける役割も果たしています。
また、噛み合わせが正しく機能することで、口や顎の筋肉、さらには消化器官がスムーズに働き、全身の健康を支えることができます。普段何気なく行っている「噛む」という行為が、健康を維持する上でとても重要な役割を担っているのです。
Treatment
噛み合わせが悪いと起こる影響・トラブル

むし歯・歯周病
歯並びが悪くなることで汚れが溜まりやすくなり、むし歯や歯周病にかかりやすくなります。
また、偏った力が歯周組織にかかることで、歯周病が発症したり悪化するリスクも高まります。
顎関節症
噛み合わせの不調が顎に負担をかけ、顎関節症になることがあります。これにより、顎の痛みや動きにくさを感じる場合があります。
詰め物・被せ物の寿命が短くなる
詰め物や被せ物に偏った力が加わることで、割れたり外れたりすることが増え、頻繁な修復が必要になる場合があります。
顔が歪む・見た目が老ける
噛む力の偏りで顔の筋肉に左右差が生じ、顔が歪んだり老けた印象を与えることがあります。
全身症状
噛み合わせが乱れることで、顎や首、肩に負担がかかり、頭痛や肩こり、耳鳴り、めまいなどの全身症状につながることがあります。
手足の痺れ
慢性的な筋肉や関節の緊張が神経に影響を与えることで、手足の痺れなどの症状を引き起こす場合があります。
認知症
噛み合わせが悪い状態が続くと、食べ物を十分に噛むことが難しくなり、脳への刺激が減少する可能性があります。噛む行為は脳を活性化させる重要な役割を果たしており、この刺激が不足すると、認知機能が低下するリスクが高まることが考えられます。
Treatment
噛み合わせが悪くなる原因

加齢による変化
年齢を重ねるにつれ、歯や顎の骨が変化し、噛み合わせに影響を及ぼすことがあります。
顎関節症
顎の関節に負担がかかることで、噛み合わせが悪化するケースが見られます。
歯並びの乱れ
歯が凸凹していたり、隙間がある状態は、噛み合わせを不安定にする要因の一つです。
歯科治療による影響
被せ物や入れ歯、ブリッジ、インプラント治療後に歯列の形態が変わることで、噛み合わせにズレが生じる場合があります。
歯ぎしり・食いしばり
無意識の歯ぎしりや食いしばりは、歯に過度な負担をかけ、噛み合わせを悪化させる原因となります。
癖や習慣の影響
舌で歯を押す癖、頬杖、片側の顎ばかり使う習慣、うつぶせ寝などが噛み合わせに悪影響を及ぼすことがあります。
口呼吸
口で呼吸をする習慣があると、顎の位置が変化しやすく、噛み合わせのズレにつながることがあります。
欠損歯の放置
失った歯をそのままにしておくと、周囲の歯が動いて噛み合わせに乱れが生じることがあります。
親知らずの放置
親知らずが正常に生えていない場合、そのままにしておくと隣接する歯や噛み合わせ全体に影響を与えることがあります。
Treatment
嚙み合わせの改善方法

生活習慣の見直し
頬杖や口呼吸、舌で歯を押す癖、うつぶせ寝、片側だけで食べる癖などは噛み合わせに悪影響を与えます。
これらの癖や習慣がある場合は、日常生活の中で意識して改善していきましょう。
マウスピース(スプリント療法)
歯ぎしりや食いしばりが原因の場合、専用のマウスピースを使用して治療を行います。
マウスピースを装着することで顎の筋肉がリラックスし、正しい噛み合わせに近づける効果が期待できます。
咬合再構成
歯科治療を用いて噛み合わせを直接調整する方法です。
具体的には、白い樹脂を使って噛み合わせを整える、あるいはエナメル質を少し削って調整することがあります。
また、被せ物や入れ歯が噛み合わせの乱れの原因となっている場合、その形状を修正することで改善します。
矯正治療
軽度の治療では改善が難しい場合、根本的なアプローチとして矯正治療を行うことがあります。
歯並びや噛み合わせを長期的に整えることで、安定した状態を目指します。
Treatment
当院の特徴

当院には、入れ歯の噛み合わせに関するお悩みで来院される方が多くいらっしゃいます。
噛み合わせの問題は、痛みを感じる部分が一か所でも、実はお口全体のバランスが影響していることが少なくありません。
そのため、患者様一人ひとりのお口の状態を丁寧に確認し、それぞれに合った治療をご提案しています。
また、院内には技工士が常駐しており、直接お口の中を確認しながら噛み合わせを細かく調整することができます。
噛み合わせでお悩みの方は気軽にご相談ください。